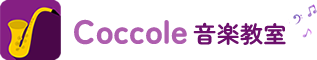こんにちは♪
千葉市幕張のサックス教室「Coccole音楽教室」
代表のサックス講師、鈴木博子です。
今日は楽譜が読めるようになるための5つのステップをお話ししたいと思います。
楽譜が苦手な方は是非参考になさってください♪
ステップ1:音符と音の名前を一致させる
- まずは、五線譜の基本を覚えましょう。五本の線と四つの間があること、線と間にはそれぞれ音符が書かれることを理解します。
- 次に、音符の形(全音符、二分音符、四分音符など)と、それぞれの音の長さを関連付けます。最初は、リズム打ちなどをしながら体で覚えるのも良いでしょう。
- そして、音の名前(ドレミファソラシ)と五線譜上の位置を一致させます。最初は、ト音記号(高い音)の楽譜から始めるのが一般的です。加線(五線譜からはみ出した線)にある音も少しずつ覚えていきましょう。
- 音部記号には他にもヘ音記号(低い音)などがありますが、まずはト音記号をしっかり理解することが大切です。(サックスの楽譜はト音記号のみで表現されます)
ステップ2:リズム譜を読む
- 音符の長さを理解したら、次はリズム譜に挑戦してみましょう。音符の長さを組み合わせて、簡単なリズムパターンを叩いたり、手拍子したりして練習します。
- 拍子記号(4/4拍子、3/4拍子など)の意味を理解し、楽譜に書かれたリズムがどのように繰り返されるのかを感じ取ることが重要です。
- 最初は、全音符、二分音符、四分音符といった基本的な音符だけで書かれたリズム譜から始め、徐々に八分音符、十六分音符などを加えていくと良いでしょう。
ステップ3:音符とリズムを結びつける
- 音の名前とリズムが個別に理解できたら、いよいよそれらを組み合わせて楽譜を読んでいきます。
- 最初は、簡単なメロディーの楽譜から挑戦しましょう。知っている童謡など、親しみやすい曲を選ぶと取り組みやすいです。
- 指で音符を追いながら、音の名前を声に出したり、楽器で音を出したりしてみましょう。
- メトロノームを使って、一定のテンポで演奏する練習も効果的です。
ステップ4:記号や音楽用語を覚える
- 楽譜には、音符やリズム以外にも様々な記号や音楽用語が出てきます。
- 臨時記号(シャープ、フラット、ナチュラル)は、音の高さを一時的に変える記号です。
- 速度記号(Allegro, Andanteなど)は、曲の速さを示します。
- 強弱記号(p, fなど)は、音の強弱を示します。
- これらの記号や用語は、楽譜を読む上で非常に重要なので、少しずつ覚えていきましょう。
ステップ5:実践と継続
- 実際に楽器を演奏したり、歌ったりしながら楽譜を読む練習を続けることが最も大切です。
- 最初はゆっくりとしたペースで、正確に読むことを心がけましょう。
- 簡単な楽譜から始めて、徐々に難しい楽譜にも挑戦していくと、達成感も得られやすく、モチベーションを維持できます。
- もし可能であれば、音楽教室に通ったり、経験のある人に教えてもらったりするのも良い方法です。
楽譜にドレミ、、、を書いてしまう方も多いのですが、それではドレミの文字ばかりを追ってしまい、楽譜に書かれている本当の意味を理解することは難しいでしょう。
音楽は、楽譜を通して作曲家の意図や表現を感じ取り、演奏を通して自分自身の感情を込めることができる、奥深い世界だと思います。
楽譜が読めるようになると、その楽しみが何倍にも広がりますよ。